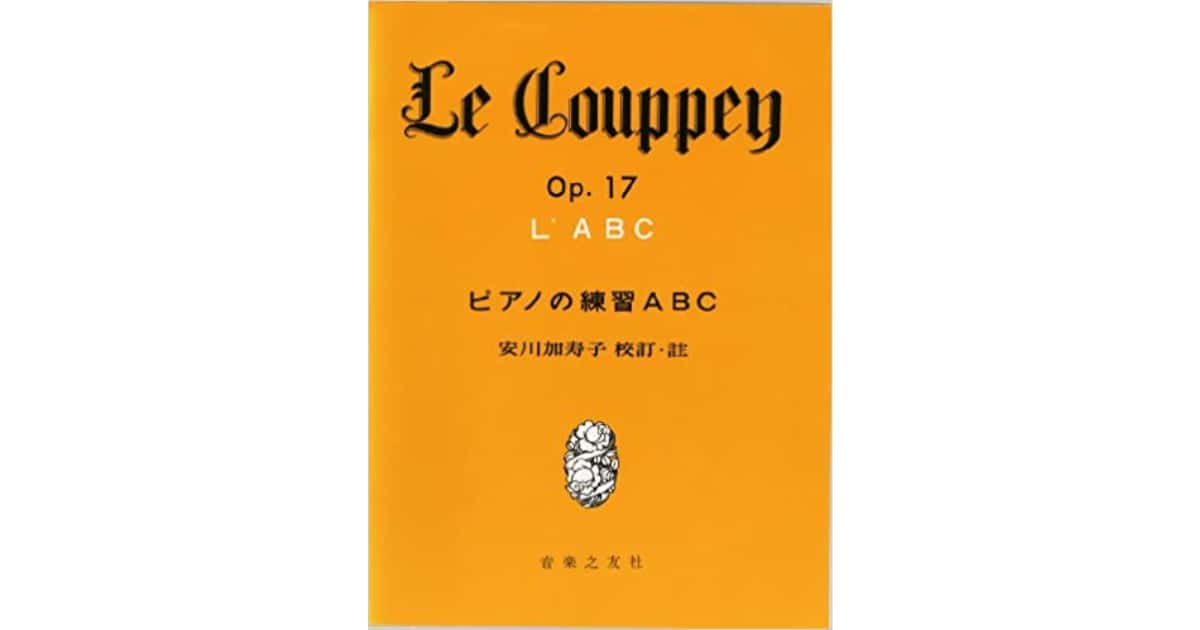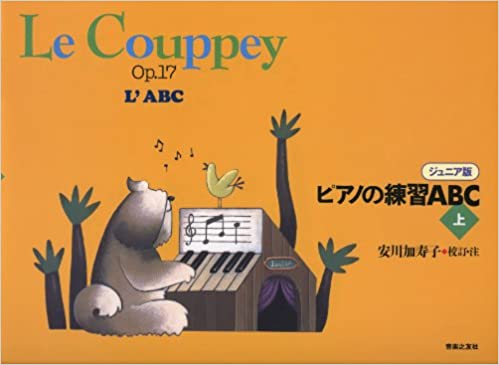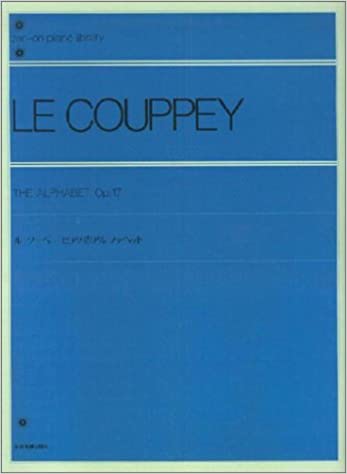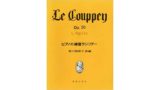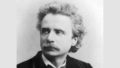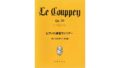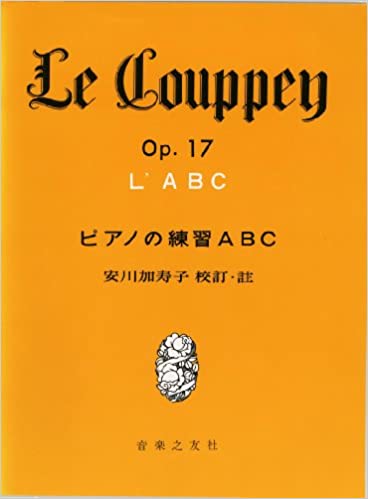
最近は初級用ピアノ教本の種類も豊富ですが、導入教材を終えてツェルニー30番に入るまでの間の教材としてかなり昔から使われてきたものに、ル・クーペの「ピアノの練習ABC(ピアノのアルファベット)」と「ラジリテー」があります。今回は長年多くのピアノ学習者に親しまれてきた教本「ピアノの練習ABC」の特徴をご紹介します。
「ピアノの練習ABC(ピアノのアルファベット)」
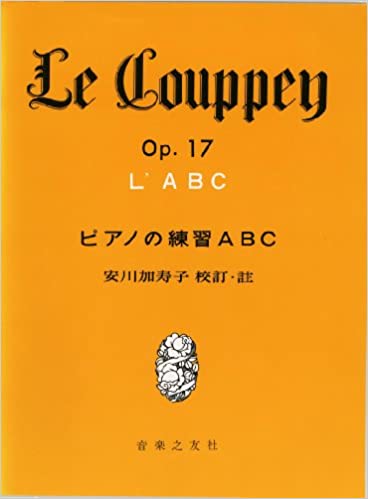
ル・クーペの「ピアノの練習ABC」は、パリ国立音楽院で学び、第二次世界大戦により日本に帰国していたピアニストの安川加寿子氏が、戦後間もなく「メトードローズ」や「ラジリテー」と共に日本に紹介しました。(「ピアノの練習ABC」の日本初版は1952年!)戦前からのバイエルとツェルニーというドイツ系の教本が主流だった当時、フランス系の教本は非常に新鮮でした。
昔からおなじみの山吹色の本は通常の楽譜サイズより大きく、レッスンかばんに入りきらないこともありますが、大きくて見やすいです。横長サイズのジュニア版(上下巻)もあります。また全音楽譜出版社からは「ピアノのアルファベット」という名称で出ていて、最近では曲ごとの練習ポイントと解説が載せられた「新こどものル・クーペ ピアノのアルファベット」が分かりやすいと人気です。
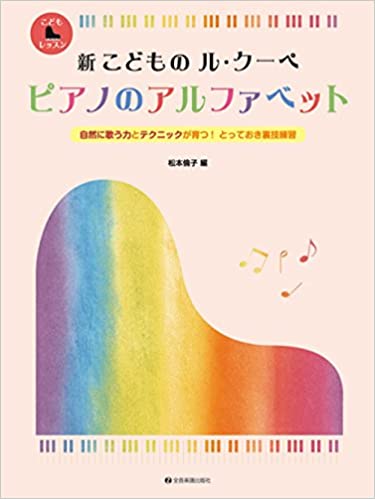
「ピアノの練習ABC」の特徴
その1:予備練習がついている。25曲の練習曲にはそれぞれ7小節の予備練習がついていて、アルファベットのA〜Z(Jは除かれている)の名前がつけられています。導入教材を終えたとはいえ、まだまだ基礎固めが必要な時期ですので、練習曲に入る前に必要なテクニックを重点的に学べるのはうれしい配慮です。

その2:メロディーや和声が美しい。バイエルやツェルニーのようなドイツ系の教本に比べて、ル・クーペの練習曲には(少し先輩のルモアーヌと同様に)洗練されて美しい響きがあります。また歌の要素がたくさん取り入れられていて、「歌うように弾く」ことを自然に身につけられるようになっています。

その3:練習の負担が少ない。予備練習と練習曲を合わせて1ページに収まる分量なので、幼いこどもだけでなく大人の学習者にとっても負担を感じさせない量と内容です。その分、ソナチネアルバムやギロックなどの併用教材を用いてより豊かな音楽性を養う余裕が生まれます。

フェリクス・ル・クーペ(Félix Le Couppey, 1811-1887)はフランスの音楽教師、ピアニスト、作曲家です。パリに生まれ、パリ国立音楽院でヴィクトル・ドゥルランに師事し、17歳の頃には和声学の助教授になっていました。のちに同音楽院の教授に就任し、亡くなる1年ほど前までピアノ教育者として指導にあたるかたわら多数のピアノ教本を出版し、ピアノ教育界に多大の貢献をしました。
収録曲をYouTubeで聴いてみよう!
練習曲5番
練習曲9番
練習曲14番
練習曲25番
「ピアノの練習ABC」(全曲)
楽譜はこちらから
いかがでしたか?長年多くのピアノ学習者に親しまれてきた「ピアノの練習ABC(ピアノのアルファベット)」で基本のテクニックと「歌うように弾く」スキルをバランスよく学んでくださいね。この本が終わったら、同じくル・クーペの「ラジリテー」でツェルニー30番に入る準備ができます。

TeeJay
ピアノ教師。海外のとある国でピアノを教えつつ感じたのは、良質の楽譜に容易に接することができる環境は本当にありがたいということ。ピアノレッスンや練習で、テクニックの習得だけでなく、音楽を表現する楽しみを味わうのに役立ついろいろな楽譜をご紹介しています。
楽譜の部屋の人気ページ